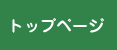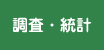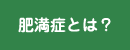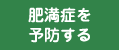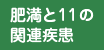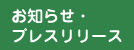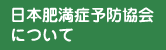「骨の健康」を守るために毎日の食事と運動が大切 健康な骨は骨粗鬆症や認知症の予防につながる
2023年04月24日

骨を健康にし、骨粗鬆症を予防するために、毎日の食事が大切という研究が発表されている。
カルシウムや良質なタンパク質、さらには野菜などからビタミンKを摂るなど、バランスの良い食事により、骨折による入院のリスクが半分に低下することが明らかになっている。
ウォーキングやランニングのような、骨に負担をかける運動は、骨の健康を改善するのに効果的という報告もある。
さらに、骨密度の低い人は、認知症を発症するリスクが42%高いという調査結果も発表された。骨の健康は、メンタルヘルスにも影響している。
骨を健康にするためにバランスの良い食事が必要
骨粗鬆症は、骨強度が低下し、骨折リスクが高まる疾患。 骨を健康にするために、食事で注意したのは、カルシウムとビタミンD、良質なタンパク質、さらにはビタミンKをバランス良く摂ることだという研究を、オーストラリアのエディス コーワン大学などが発表している。 カルシウムは、乳製品・大豆製品・緑黄色野菜・海藻・魚などに多く含まれる。カルシウムは乳製品から効率良く摂ることができる。コップ1杯の牛乳(200mL)に200mgのカルシウムが含まれている。 また、丈夫な骨をつくるために、ビタミンDも不可欠だ。ビタミンDが著しく足りていないと、骨折リスクが大幅に上昇するという報告がある。 ビタミンDの不足を防ぐには、ビタミンDを多く含む食品を積極的に食べるとともに、日光を適度に浴びることも大切だ。 さらに、ビタミンKは骨をつくる働きを促す。ビタミンKは、納豆などの大豆食品、キャベツ・ホウレンソウ・小松菜などの葉物野菜、ブロッコリーなどの緑黄色野菜、豆類、海藻類、卵などに多く含まれる。野菜などからビタミンKを摂っていると骨折リスクが低下
骨を健康に保ち、骨折などを防ぐために、ビタミンKをしっかりと摂ることも大切だ。 「ビタミンKを十分に摂ることで、年齢を重ねてから、股関節骨折などのリスクを下げることを期待できます」と、同大学栄養・健康・イノベーション研究所のマーク シム氏は言う。 同研究所の調査で、ビタミンKを摂取している女性は、そうでない女性に比べ、骨折するリスクが31%低いことが示された。研究グループは、70歳以上の高齢者1,373人を対象に、14.5年以上追跡して調査した。 その結果、ビタミンKをもっとも多く摂取していた人は、骨折による入院のリスクがほぼ半分に減少した。1食で125g以上の葉物野菜や緑黄色野菜を食べることが勧められるという。 「ビタミンKが骨吸収を阻害し、骨の健康を促進している可能性があります。ビタミンKは、骨の形成に必要なオステオカルシンなどを活性化するのにも必要です」と、シム氏は指摘する。 「ホウレンソウ、ブロッコリー、キャベツ、ケールなどの野菜を毎日食べることをお勧めします」としている。骨を丈夫にするために毎日の運動も大切

骨に負荷をかける運動が骨を丈夫にして糖代謝も改善
研究グループは、トレーニングを受けた17人のランナーを対象に、マラソンを走る前後に体の状態を調べた。 骨から血流へのカルシウムの放出や、骨を弱める骨吸収に加えて、骨形成やエネルギー調節に関連するホルモンの変化を測定した。 このうち、「オステオカルシン」と「P1NP」は、骨形成に関わる重要なタンパク質だ。さらに、糖代謝に関わる重要なホルモンである「インスリン」や、「グルカゴン」や「レプチン」などの値も調べた。 その結果、マラソンランナーは、レース終了時にはグルカゴンの値が高く、レプチンとインスリンの値が低くなっていることが分かった。インスリンの低下は、オステオカルシンとP1NPの低下と関連していた。 「骨形成に関わるタンパク質であるオステオカルシンは、インスリンを分泌する膵臓のβ細胞とも通信し、体の糖代謝を調整しているとみられます」と、ロンバルディ氏は言う。 「ウォーキングやランニングなどの、骨に物理的な負荷をかける運動は、骨組織を刺激して膵臓にシグナルを送り、糖代謝を良くしたり、エネルギー需要を満たすのに役立っていると考えられます」としている。 骨と体の代謝は相互に作用しあっている。骨の代謝について理解を深めることで、糖尿病と骨粗鬆症の関連が分かり、糖尿病のより良い治療にもつながると考えられる。骨密度の低い人は認知症リスクも42%高い
骨密度が低い人は、そうでない人に比べて、認知症を発症するリスクが高いという調査結果を、米国神経学会(AAN)が発表した。 「高齢者の多くは、骨密度の低下と認知症の発症という、2つのリスクを同時にもっています。不健康な食事や運動不足により、2つの疾患のリスクは上昇します」と、オランダのエラスムス ロッテルダム大学疫学部のモハマド アルファン イクラム教授はいう。 「認知症にいたるまでの期間に起こる骨減少について、よく分かっていませんでしたが、今回の研究で、骨減少は認知症のリスクが高いことと関連していることが示されました」としている。 研究グループは、認知症を発症していない平均年齢72歳の高齢者3,651人を対象に、平均11年追跡して調査した。 骨密度を調べるために、参加者に骨のスキャンやX線検査を行い、4~5年ごとに認知症の検査なども行った。期間中に19%が認知症を発症した。骨の健康はメンタルヘルスにも影響 若いうちから対策を
その結果、骨密度の低い人は、骨密度の高い人に比べ、10年以内に認知症を発症するリスクが42%高いことが明らかになった。 「これまでも、食事や運動などの生活スタイルが、認知症のリスクに影響をもたらし、骨の健康にも影響することが示されています」と、イクラム教授はいう。 「骨の健康と認知症の関連について、さらに研究を重ねる必要がありますが、骨減少が認知症のリスクを知るための指標になる可能性があります」。 「とくに高齢の人は、骨の健康を高めるための生活改善を、早い段階ではじめる必要があります」としている。 Catch a break: higher vitamin K intake linked to lower bone fracture risk late in life (エディス コーワン大学 2022年11月28日)Dietary Vitamin K1 intake is associated with lower long-term fracture-related hospitalization risk: the Perth longitudinal study of ageing women (Food & Function 2022年9月12日)
Calcium And Vitamin D May Not Be The Only Protection Against Bone Loss (米国内分泌学会 2008年12月4日)
Running may be better than cycling for long-term bone health (欧州内分泌学会 2016年5月30日)
Is bone health linked to brain health? (米国神経学会 2023年3月22日)
Association of Bone Mineral Density and Dementia: The Rotterdam Study (Neurology 2023年3月22日)
[ TERAHATA / 日本医療・健康情報研究所 ]
掲載記事・図表の無断転用を禁じます。 ©2006-2025 soshinsha. 日本医療・健康情報研究所
- 11月11日
- 非肥満者では糖尿病発症前に体重が減少する傾向を発見【富山大学】
- 11月11日
- 「メタボ健診」で国保加入現役世代の生活習慣病罹患率が約10%減少
- 10月29日
- 「食行動のクセ」がGLP-1受容体作動薬の2型糖尿病治療効果と関連 岐阜大学・京都大学ら
- 10月29日
- 働く世代の足腰の健康がカギ ロコモとメタボの意外な関係を解明【昭和医科大学】
- 09月25日
- 健康関連アプリ活用で特定保健指導の成果向上 利用率・代謝改善に有意差
- 09月25日
- 令和4年度特定健診受診者「メタボ該当者」は14.8% 高齢層で高水準続く(健保連)
- 08月25日
- 肥満と糖尿病への積極的な対策を呼びかけ 中国の成人男性の半数が肥満・過体重 体重を減らしてリスク軽減
- 08月25日
- 1日7000歩のウォーキングが肥満・がん・認知症・うつ病のリスクを大幅減少 完璧じゃなくて良い理由
- 07月28日
- 日本人労働者の3人に1人が仕事に影響する健康問題を経験 働きながら生産性低下を防ぐ対策が必要
- 野菜摂取量の平均値は、256.0g(男性262.2g、女性250.6g)。野菜摂取量は有意に減少 令和5年(2023)「国民健康・栄養調査」結果より
- 糖尿病が強く疑われる人は、男性16.8%、女性8.9% 令和5年(2023) 「国民健康・栄養調査」の結果より
- 肥満の人は、男性31.5%、女性21.1%。やせの人は、男性4.4%、女性12.0%(20歳代女性20.2%) 令和5年(2023)「国民健康・栄養調査」の結果より
- 特定健診(40~74歳)受診者約3,017万人のうち、メタボリックシンドローム該当者は16.6%(男性13.3%、女性3.2%)、予備群該当者は、12.3%(男性 9.7%、女性2.6%) 令和4年(2022)「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」の結果より
- メタボリックシンドロームが強く疑われる人は、男性28.2%、女性10.3% 予備群の人は、男性 23.8%、女性7.2%-令和1年(2019)「国民健康・栄養調査」の結果より