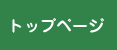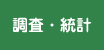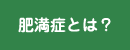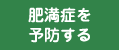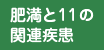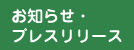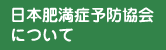リレーコラム「教えて!肥満症」
第2回 温故知新;日本人の肥満症
2025年11月14日
下村 伊一郎
日本肥満症予防協会 副理事長
大阪大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科学 教授
はじめに
1960年代の高度経済成長期以降、日本人の生活は欧米化し体重も増え、糖尿病や脂質異常・高血圧など、肥満に伴う疾患が増え、かつ狭心症や心筋梗塞と言った動脈硬化性疾患も増えました。
しかし、欧米人ほどまでの肥満にはなっていないのに関わらず、上記疾患が増え続けたという医学的には不思議な事実がありました。
1 内臓脂肪型肥満と皮下脂肪型肥満
1980年代、CTスキャンを用いて全身の脂肪の分布を調べる研究が始まり、お腹の中の脂肪・内臓脂肪が増える内臓脂肪型肥満と皮下の脂肪が増える皮下脂肪型肥満があることがわかってきました。
そして、同じ肥満度でも、皮下脂肪型肥満はあまりいろいろな病気にならず、したがって皮下脂肪は余ったエネルギーを安全に溜め込んでおく倉庫のような働きをする脂肪であること、一方、内臓脂肪型肥満は様々な疾患と連動することから蓄積内臓脂肪は病気に直結する脂肪であることがわかってきました。
そして日本人をはじめとした東アジア人は、余ったエネルギーは皮下脂肪には溜まりにくく内臓脂肪に溜まりやすいという遺伝的素因・体質を持っています。
2 メタボリックシンドローム、特定メタボ健診・保健指導
日本人では肥満度が25未満のいわゆる正常体重者でも、お腹が出てきて内臓脂肪が溜まっている場合には様々な肥満に伴う疾患が多いということがわかってきて、肥満・非肥満に関わらず内臓脂肪がたまりそれに伴うと考えられる疾患のある場合をメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)と名付けられました。
そしてこのメタボリックシンドローム・お腹まわりをターゲットにして全国民レベルで生活習慣病を減らそうという動きが特定メタボ健診・特定保健指導という国策・社会実装に繋がり、効果も実証され、日本は世界有数の健康促進立国として認識されるようになりました。
3 日本人肥満症の病態

図 日本人肥満症の病態
余ったエネルギーが皮下脂肪にたまらず内臓脂肪にたまるとなぜ病気になっていくのかについて、たくさんの研究がなされ、大きく2つの病態があることがわかってきました。
1つは、脂肪組織で作られる様々な分泌因子・アディポサイトカインの産生異常です。特に蓄積した内臓脂肪で起こる酸化ストレス産生上昇・炎症性サイトカイン産生上昇、アディポネクチン産生低下といったアディポサイトカイン産生異常は、脂肪組織局所また全身に波及し、糖尿病、脂質異常症、高血圧、動脈硬化性疾患に直結することがわかってきました。
2つ目は、臓器内脂肪蓄積で、蓄積した内臓脂肪から遊離脂肪酸が分泌され血液を介して様々な実質臓器に流れ込み、慢性的高インスリン血症と相まって、臓器内への中性脂肪蓄積が引き起こされます。
これまで脂肪肝そしてそれに引き続く脂肪肝炎・肝硬変は知られていましたが、最近では、同様の現象が、肝臓同様インスリンの作用する骨格筋、インスリンを作る膵臓・膵島、また、心臓、狭心症や心筋梗塞の現場となる冠動脈、腎臓、脾臓など、多くの重要な臓器にも起こり、広範な臓器/組織での臓器内脂肪蓄積病態(脂質蓄積/炎症/線維化・機能低下、等)の存在が明らかとなってきています。
おわりに
1970年ごろ、すなわち前の大阪万博のころに日本人が食べていた食事が、世界の歴史上存在した最強の長寿食であるという話しがあります(味噌汁・漬物など塩分は少し多すぎるのですが)。野菜・根菜・海藻・きのこ・魚が中心で、肉(ほとんどが鶏肉と豚肉)は週に2回くらい、そんな時代でした。
現在は、野菜が少なく、肉・油ものが多くなり、運動量も少なく、カロリー過剰状態で、皮下脂肪にエネルギーをためにくく内臓脂肪をためやすい日本人にとっては非健康的・不利な社会環境と言えます。
しかし、一方、蓄積した内臓脂肪は皮下脂肪に比して、生活習慣改善・向上すなわち適切な食事運動療法に反応して減りやすく、それに伴い上で述べたアディポサイトカイン産生異常や臓器内脂肪蓄積の病態、すなわちいろいろな病気やその程度が五月雨的に減り改善することも日本人肥満症の特徴であることもわかってきています(図)。
私の仕事部屋は大阪北部郊外の大学の建物の7階にあります。ちょうど私の部屋から1970年大阪万博シンボルの「太陽の塔」の背中が見えます。「太陽の塔」が南を向き、都心の新しい2025年大阪万博に向けて語っていたのは、「新しい進歩も大事だけど、あの頃の生活を思い返すことも日本人の健康と幸せにつながるよ!」ということだったかと感じています。
温故知新。
(2025年11月)