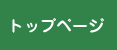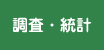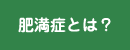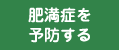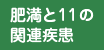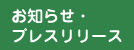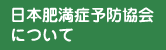「肥満の人は生活がだらしなく自己管理ができない」は誤解 「肥満症診療ガイドライン2022」
2022年12月15日

日本肥満学会は、「肥満症診療ガイドライン2022」を発刊した。6年ぶりとなる改訂で、肥満と肥満症に関するスティグマの解消を含め、最新の知見が取り入れられた。新たに「高度肥満症」、「小児の肥満と肥満症」、「高齢者の肥満と肥満症」、「肥満症治療薬の適応および評価基準」の章も設けられた。
新たに設けられた「第1章 肥満症治療と日本肥満学会が目指すもの」を一読するだけでも、肥満症の診断と治療、その目標について最新のエッセンスを知ることができる。
成人だけでなく小児や高齢者の肥満にも対応
日本肥満学会は2000年に医療を必要とする肥満である「肥満症」の概念を提唱し、肥満症の診断基準を策定した。それ以後、この概念にそった診療を推奨してきた。このほど6年ぶりにガイドラインを改訂し、「肥満症診療ガイドライン2022」として発刊した。 新たに「高度肥満症」、「小児の肥満と肥満症」、「高齢者の肥満と肥満症」、「肥満症治療薬の適応および評価基準」の章が設けられた。肥満と肥満症に関するスティグマの解消を含め、最新の知見が取り入れられている。 新たに設けられた「第1章 肥満症治療と日本肥満学会が目指すもの」を一読するだけでも、肥満症の診断と治療、その目標について最新のエッセンスを知ることができる(序文と第1章は日本肥満学会サイトで、無料で公開されている)。 2016年以降、小児や高齢者の肥満と肥満症を含め、国内外の知見は増えている。日本でも、高度肥満症を対象とした外科療法(減量・代謝改善手術)が保険収載され、肥満症治療薬の臨床開発も進んでおり、日本の肥満症診療は大きな変化を遂げつつある。 日本糖尿病学会・日本肥満症治療学会・日本肥満学会は2021年に、「日本人の肥満2型糖尿病患者に対する減量・代謝改善手術に関するコンセンサスステートメント」を3学会合同で発表した。 長らく変化に乏しかった薬物療法でも、新たな肥満症治療薬の登場が待たれている。肥満症の治療は、従来はエネルギー制限療法や対症療法にとどまっていたが、病因遺伝子の解明にともない特異的な薬剤介入の道が開かれる可能性も期待されている。肥満と肥満症に対する偏見や誤解にも取り組む
日本人は欧米人に比べ、極端な肥満は少なく、軽度の肥満が多い。しかし、わずかに太っただけでも、2型糖尿病や脂質異常症、心筋梗塞、脳卒中、腎臓病などの発症率は高くなることが知られている。同学会は、内臓脂肪の蓄積が、健康障害をもたらす病態の中心にあるとして、その重要性を一貫して論じている。 肥満に対する保健指導などでは、肥満の原因は必要以上に食習慣などの個人の生活上の要因に帰せられている傾向がみられるとしている。さらに、「自己管理能力が低いから肥満になる」といった偏見も少なくない。 たしかに肥満やメタボの多くは、食事や運動などの生活スタイルの改善により、内臓脂肪がたまるのを防げ改善できることが知られている。しかし、肥満と肥満症の背景には、遺伝(体質)によるものと、環境によるものの両方があり、生育や発達での要因、社会的な要因も影響しているので、個人の努力だけでは対応できなくなるおそれもある。 「スティグマ」とは、特定の事象や属性をもった個人や集団に対する、間違った認識や根拠のない認識にもとづく差別や偏見のこと。 同学会では、「肥満には、社会的スティグマに加え、肥満を自分自身の責任と考える個人的スティグマもあり、医療者と患者のあいだに治療の認識の差がある」と指摘。 こうした肥満に対するスティグマは、心理的負担や社会的不利益をもたらすだけでなく、「自己管理の問題であって、医療を受ける対象ではない」といった誤った理解を引き起こし、適切な治療の機会が奪われるのにつながるとしている。 「"肥満症診療ガイドライン2022"では、肥満症をもつ人の福祉の向上のために肥満学会が目指す社会的な取り組みなどにもふれています。発刊を機に、肥満症の現況と診療の進歩が社会的に広く認知されることを期待しています」と、同学会では述べている。 一般社団法人 日本肥満学会 日本人の肥満2型糖尿病患者に対する減量・代謝改善手術に関するコンセンサスステートメント (日本糖尿病学会)|
日本肥満学会「肥満症診療ガイドライン2022」 目次
| ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
[ TERAHATA / 日本医療・健康情報研究所 ]
掲載記事・図表の無断転用を禁じます。 ©2006-2026 soshinsha. 日本医療・健康情報研究所
- 12月18日
- 20~30代低体重女性で腸内細菌叢の多様性が低下 食事内容が同じでも違いが生じることを解明
- 12月18日
- 寿司のネタとシャリは分けて食べるべき?~血糖値への影響を調べた研究結果~
- 11月11日
- 非肥満者では糖尿病発症前に体重が減少する傾向を発見【富山大学】
- 11月11日
- 「メタボ健診」で国保加入現役世代の生活習慣病罹患率が約10%減少
- 10月29日
- 「食行動のクセ」がGLP-1受容体作動薬の2型糖尿病治療効果と関連 岐阜大学・京都大学ら
- 10月29日
- 働く世代の足腰の健康がカギ ロコモとメタボの意外な関係を解明【昭和医科大学】
- 09月25日
- 健康関連アプリ活用で特定保健指導の成果向上 利用率・代謝改善に有意差
- 09月25日
- 令和4年度特定健診受診者「メタボ該当者」は14.8% 高齢層で高水準続く(健保連)
- 08月25日
- 肥満と糖尿病への積極的な対策を呼びかけ 中国の成人男性の半数が肥満・過体重 体重を減らしてリスク軽減
- 野菜摂取量の平均値は、256.0g(男性262.2g、女性250.6g)。野菜摂取量は有意に減少 令和5年(2023)「国民健康・栄養調査」結果より
- 糖尿病が強く疑われる人は、男性16.8%、女性8.9% 令和5年(2023) 「国民健康・栄養調査」の結果より
- 肥満の人は、男性31.5%、女性21.1%。やせの人は、男性4.4%、女性12.0%(20歳代女性20.2%) 令和5年(2023)「国民健康・栄養調査」の結果より
- 特定健診(40~74歳)受診者約3,017万人のうち、メタボリックシンドローム該当者は16.6%(男性13.3%、女性3.2%)、予備群該当者は、12.3%(男性 9.7%、女性2.6%) 令和4年(2022)「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」の結果より
- メタボリックシンドロームが強く疑われる人は、男性28.2%、女性10.3% 予備群の人は、男性 23.8%、女性7.2%-令和1年(2019)「国民健康・栄養調査」の結果より