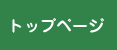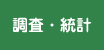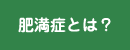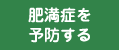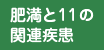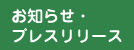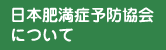【新型コロナ】流行前に比べて38%の人が体重増加 9割以上は「やせたい」と希望
2022年12月15日

新型コロナの流行前に比べて、体重が増えたという人は38%に上ることが、47都道府県の男女9,400人を対象に行われた調査で示された。
肥満には遺伝的、社会的、環境的要因など、さまざまな要因が関わっており、決して個人だけの責任ではない。
「肥満や肥満症を予防・改善するためには、現在よりも体重を増やさないなどの自己管理が重要です」と、研究者は述べている。
肥満や肥満症について相談した人はたったの13%
ノボ ノルディスク ファーマは、全国47都道府県の20~75歳の男女9,400人を対象に、「肥満」と「肥満症」に関する意識実態調査を実施した。 調査では、新型コロナの流行前に比べて、体重が増えたという人は38%に上ることが分かった。肥満は、新型コロナの重症化リスクのひとつとして注目されているが、2型糖尿病や心血管疾患をはじめとする多くの疾患のリスク要因でもあり、予防と対策が重要となる。 さらに、「肥満」および「肥満症」の疑いがある人の95%は、今よりやせたいと考えていて、うち半数近くは10kg以上やせたいと思っているものの、肥満のために医療機関に行ったり、医師に相談したことがある人は13%と非常に少ないことも示された。 また、「肥満」と「肥満症」の違いを知る人は、全体の3分の1以下にとどまるという。「肥満症」の定義を知っている人も、「なんとなく」を含めても全体の9%と少なかった。太っていることが原因で他人からネガティブなことを言われた経験のある人は48%と半数近くに上った。 調査は、BMI(体格指数)が25以上の男女を対象に、2022年9月にインターネットで行ったもので、昨年に続いて2回目となる。肥満症や肥満症は個人だけの責任ではない
調査結果について、日本肥満学会理事長の横手幸太郎先生(千葉大学大学院医学研究院内分泌代謝・血液・老年内科学教授)は次のように述べている。
「BMI 25以上は、身体に脂肪が過剰に蓄積した"肥満"と判定します。しかし、それだけでは医学的な治療の対象にはなりません。BMIが25以上で、かつ、2型糖尿病や脂質異常症など、肥満に関連する健康障害を合併していたり、内臓脂肪の蓄積がみられる場合に"肥満症"という病気と診断し、減量治療を行います」。
「本調査では、肥満を抱える方の多くが痩せたいと思い、実際に減量に取り組んでいる様子が伺えます。肥満から肥満症になってしまうことを予防するためには、現在よりも体重を増やさないなどの自己管理が重要となります。また、肥満の中で、医学的な減量治療が必要な肥満症を的確に診断することが大切であり、肥満症と診断される健康障害のいくつかは健康診断でも知ることができます」。
「肥満には遺伝的、社会的、環境的要因など、さまざまな要因があり、決して個人だけの責任ではありません。肥満や肥満症の方は、1人で悩む必要はなく、医療従事者をはじめ、家族や周りの人のサポートを得ながら減量に取り組むとよいでしょう」。
ノボ ノルディスク ファーマでは、「引き続き、肥満が長期にわたって与える影響について啓発していきます。また、本意識調査では、2021年の調査結果同様、"肥満"と"肥満症"の違いを知る人が少なかった一方、約半数の人が太っていることが原因で他人からネガティブなことを言われた経験があると回答しました」と述べている。
「社会全体の肥満や肥満症に対するスティグマを減らすべく、肥満症が長期的な医学的管理を必要とする慢性疾患であるという正しい理解の浸透に向け、より一層尽力してまいります」としている。
* 「スティグマ」とは、特定の事象や属性をもった個人や集団に対する、間違った認識や根拠のない認識にもとづく差別や偏見のこと。
9割以上の人は「今よりやせたい」と思っている
なお、肥満の判定では、体格指数(BMI)が用いられ、日本ではBMI 25以上が「肥満」と定義されている。日本肥満学会の定めた基準では、18.5未満が「低体重」、18.5以上25未満が「普通体重」、25以上が「肥満」。さらに、肥満はその度合いによって「肥満 (1度)」から「肥満 (4度)」に分類される。 一方、「肥満症」は、肥満で、かつ肥満と関連する健康障害がある、または内臓脂肪蓄積があり、医学的に減量が必要な慢性疾患と定義されている。 それ以外の調査の主な内容は次の通り――。- 「今よりやせたい」と思っている人は95%に上り、「10Kg以上やせたい」という人は49.0%、「20Kg以上やせたい」という人も16%に上った。もっとも回答が多かったのは「10kg以上~15kg未満」で23%。
- 新型コロナの流行前に比べて、体重が増えたという人は38%。増えた人が多い都道府県は埼玉県・石川県・熊本県。
- 自身の現在の体型について、「満足している」という人は4%にとどまり、95%が「今よりやせたい」と回答した。「今よりやせたい」という人が多い都道府県は茨城県・栃木県・新潟県・静岡県で、それぞれ98%を超えている。
- 今までに何らかの「減量」や「ダイエット」に取り組んだことがある人は86%に上り、これまでに「10回以上」のダイエットに挑戦したという人も14%に上る。
- 行ったことがある減量法の1位は「間食やおやつを控える」(52%)、2位「食事制限」(47%)、3位「食べ方に気をつける」(38%)。
- 「減量」や「ダイエット」に取り組んだことがあるなかで、成功しなかったり、リバウンドした経験がある人は94.6%に上る。減量が成功しなかった理由1位は「ストレスがたまった」(43%)、2位「面倒になった」(42%)、3位「効果が実感できなかった」(38%)。
- 「肥満」の悩みについて医療機関に行ったり、医師に相談したりしたことがある人は13%、減量法として「病院に行き、医師に相談する」と答えた人も4%にとどまる。相談しない理由でもっとも多いのは「『肥満』は自己責任だと思うから」で36%。相談した理由でもっとも多いのは「健康診断で勧められたから」で48%。
- 太っていることが原因で他人からネガティブなことを言われた経験のある人が48%と半数近くに上る。言われたネガティブなことで多かったのは「運動不足である」(49%)、「だらしがない、怠惰である」(39%)、「食生活や生活習慣が乱れている」(33%)など。
肥満に悩む人々に、減量のメカニズムなど、肥満に関する科学とともに、肥満・肥満症の正しい知識と体重管理をサポートするハウツー情報を紹介しているサイト。
動画 (Truth About Weight-肥満症を知る-)
肥満症を管理するためには、正しい情報にふれ、正しい知識を身に着けることが重要として、肥満改善をサポートしている専門家、悩みを共有する人々の体験談など、肥満症に関する理解が深まる情報をさまざまな角度から動画コンテンツで紹介している。
肥満症 (ノボ ノルディスク ファーマ)
[ TERAHATA / 日本医療・健康情報研究所 ]
掲載記事・図表の無断転用を禁じます。 ©2006-2025 soshinsha. 日本医療・健康情報研究所
- 12月18日
- NEW20~30代低体重女性で腸内細菌叢の多様性が低下 食事内容が同じでも違いが生じることを解明
- 12月18日
- NEW寿司のネタとシャリは分けて食べるべき?~血糖値への影響を調べた研究結果~
- 11月11日
- 非肥満者では糖尿病発症前に体重が減少する傾向を発見【富山大学】
- 11月11日
- 「メタボ健診」で国保加入現役世代の生活習慣病罹患率が約10%減少
- 10月29日
- 「食行動のクセ」がGLP-1受容体作動薬の2型糖尿病治療効果と関連 岐阜大学・京都大学ら
- 10月29日
- 働く世代の足腰の健康がカギ ロコモとメタボの意外な関係を解明【昭和医科大学】
- 09月25日
- 健康関連アプリ活用で特定保健指導の成果向上 利用率・代謝改善に有意差
- 09月25日
- 令和4年度特定健診受診者「メタボ該当者」は14.8% 高齢層で高水準続く(健保連)
- 08月25日
- 肥満と糖尿病への積極的な対策を呼びかけ 中国の成人男性の半数が肥満・過体重 体重を減らしてリスク軽減
- 野菜摂取量の平均値は、256.0g(男性262.2g、女性250.6g)。野菜摂取量は有意に減少 令和5年(2023)「国民健康・栄養調査」結果より
- 糖尿病が強く疑われる人は、男性16.8%、女性8.9% 令和5年(2023) 「国民健康・栄養調査」の結果より
- 肥満の人は、男性31.5%、女性21.1%。やせの人は、男性4.4%、女性12.0%(20歳代女性20.2%) 令和5年(2023)「国民健康・栄養調査」の結果より
- 特定健診(40~74歳)受診者約3,017万人のうち、メタボリックシンドローム該当者は16.6%(男性13.3%、女性3.2%)、予備群該当者は、12.3%(男性 9.7%、女性2.6%) 令和4年(2022)「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」の結果より
- メタボリックシンドロームが強く疑われる人は、男性28.2%、女性10.3% 予備群の人は、男性 23.8%、女性7.2%-令和1年(2019)「国民健康・栄養調査」の結果より