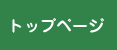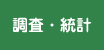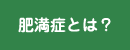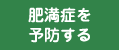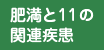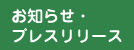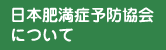3月4日は世界肥満デー 体重はライフステージを通して変化 もっとも長生きするのはやせ気味の人
2023年03月02日

3月4日は「世界肥満デー(World Obesity Day)」だ。
肥満や過体重は、心臓病や高血圧、2型糖尿病などのリスクを高め、死亡リスクも高めることが知られている。
肥満が健康リスクになるのは、体重が極端に多い高度な肥満の人のみだと思われがちだが、それは間違いで、少し太っただけでも、人によっては健康に悪い影響があらわれるという研究が発表された。
もっとも長生きするのは、BMIが18.5~22.5とやせ気味の人であることも明らかになった。
肥満であった一時期が人生にあっただけで、たとえその後に体重を減らしても、年齢を重ねると病気になりやすい可能性があるという。やはり、若い頃から健康的な体重を維持することが大切だ。
3月4日は世界肥満デー 肥満はさまざまな健康問題の原因に
3月4日は世界肥満連合(WOF)が提唱する「世界肥満デー(World Obesity Day)」だ。 肥満や過体重は世界的に増えている。世界の20億人が肥満か過体重で、有効な対策をしないと、2035年までに世界の4人に1人が肥満になるとWOFは予測している。 肥満はさまざまな健康問題を引き起こす。肥満と過体重により、世界の医療費などの経済に590兆円(4.32兆ドル)の負担がもたらされているとしている。 肥満や過体重は、健康的な体重の人に比べ、死亡リスクが高いという調査結果を、米コロラド大学が発表した。死亡リスクは、過体重の人は22%、肥満の人は2倍に、それぞれ上昇するという。 「肥満が健康リスクになるのは、体重が極端に多い高度な肥満の人のみだと思われがちですが、それは間違いで、少し太っただけでも、人によっては健康に悪い影響があらわれます」と、研究者は警笛を鳴らしている。
世界肥満デー2023
世界肥満連合(WOF)が公開しているビデオ
世界肥満連合(WOF)が公開しているビデオ
「肥満のパラドックス」に挑む
肥満の判定は、体格指数(BMI)により行われることが多い。BMIは〔体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)〕という式で求められる。 肥満や過体重は、心臓病や高血圧、2型糖尿病などのリスクを高め、死亡リスクも高めることが知られている。 一方で、体格指数(BMI)が高いことが、必ずしも死亡率を高めるわけではない。むしろ、BMIが25~30の「小太り」の人が、もっとも死亡率が低いという報告もある。 これは、「肥満のパラドックス」とも呼ばれており、肥満と死亡リスクの関連はU字型の曲線を示しており、小太りの人はむしろ長生きすることを示した調査が多い。 ただし、「低体重」(BMIが18.5未満)の人と、高度の肥満(BMIが35以上)の人は、それぞれ死亡リスクが高くなるので、注意が必要となる。 関連情報ライフステージを通して体重は変化
研究グループは、45~85歳の成人1万7,784人が参加した、米国国民健康栄養調査(NHANES)の1988年~2015年のデータを解析した。 「現状の体重やBMIのみをみて、ご自分の健康状態を知る目安にすると、健康リスクについて、見落としてしまう可能性があります」と、コロラド大学で社会人口学を研究しているライアン マスターズ氏は言う。 「多くの人は、ライフステージを通して体重が変化しています。就職・結婚・出産・子育て・子供の独立・定年退職など、ライフステージにより体重は変化していることが多いのです」。 調査では、「健康的」な体重と判定された人々の20%は、10年前に過体重や肥満であった時期があり、そうした人々はずっと体重が安定していた人々に比べ、健康状態が悪化しやすいことも分かった。 つまり、肥満であった一時期が人生にあると、たとえその後に体重を減らしたとしても、年齢を重ねると病気になりやすい可能性があるという。やはり、若い頃から健康的な体重をずっと維持することが大切だ。ライフステージを通して体重に注意する必要が
「一生のうちに肥満や過体重である時期があると、その後に急速な体重減少につながる病気を発症しやすくなる可能性も考えられます」と、マスターズ氏は指摘する。 さらに、過体重と判定された人の37%と、肥満と判定された人の60%は、10年前はBMIが低くやせていたことが分かった。 健康的な体重を維持していた時期が長く、最近になり体重が増えたという人は、現状では健康状態は良好であることが多かった。 「多くの人にとって肥満や過体重は、やはり健康リスクになります。小児・若年期、中年期、高齢期とライフステージを通して、体重やBMIの変化に気を配っている必要があります」としている。「内臓脂肪型肥満」にもご注意
体についている脂肪の組成にも注意する必要があるという。これも、BMIのみをみていると見落としてしまうことだ。 腹筋の内側、腸などの周りにつく内臓脂肪が多いのが「内臓脂肪型肥満」。このタイプの肥満だと、へそ周りがぽっこりと出た体型になる。 内臓脂肪型肥満のある人は、高血圧や2型糖尿病、さらには心筋梗塞などさまざまな病気を、中年期から起こしやすい。そうした人は、若いうちから体重を減らし適正に管理することが勧められる。 「たとえば、俳優のトム クルーズさんは、身長は170センチで、体重は91キロ。BMIは31.5で、"肥満"と判定されますが、彼はとても筋肉質な体をしているのです。そうした人は健康リスクが低いとみられます」と、マスターズ氏は指摘する。もっとも長生きするのはやせ気味の人
研究グループが今回の研究で、BMIに関連するこうしたバイアスの影響を取り除いて解析した結果、死亡リスクがもっとも低いのは、BMIが18.5~22.5とやせ気味の人であることが明らかになった。 「"BMIが上昇して肥満になっても、非常に高いレベルに達するまで死亡リスクは上昇しない。少し太っているくらいであれば、むしろ健康にとって利点となる"という考え方をする人は少なくありませんが、これは間違いである可能性があります」と、マスターズ氏は指摘する。 「現状の体格指数(BMI)のみを頼りにして、健康状態について判定したり生活指導することには、落とし穴があると考えられます」としている。 「米国で亡くなる人の6分の1は、過体重や肥満が原因である可能性があります。そうした人々に、食事や運動など、健康的な生活スタイルを身につけてもらうことが大切です」。 「スナックや菓子、清涼飲料、ジャンクフードなど、安価ではあるがカロリーが高く栄養バランスも悪い超加工食を食べ過ぎていたり、座ったまま過ごす時間が長い不活発な生活をしていると、肥満や過体重につながりやすいので注意が必要です」と、マスターズ氏は述べている。 Excess weight, obesity more deadly than previously believed (コロラド大学ボルダー校 2023年2月23日)Sources and severity of bias in estimates of the BMI-mortality association (Population Studies 2023年2月9日) 世界肥満デー
Obesity and overweight(世界保健機構 2021年6月9日)
[ TERAHATA / 日本医療・健康情報研究所 ]
掲載記事・図表の無断転用を禁じます。 ©2006-2026 soshinsha. 日本医療・健康情報研究所
- 12月18日
- 20~30代低体重女性で腸内細菌叢の多様性が低下 食事内容が同じでも違いが生じることを解明
- 12月18日
- 寿司のネタとシャリは分けて食べるべき?~血糖値への影響を調べた研究結果~
- 11月11日
- 非肥満者では糖尿病発症前に体重が減少する傾向を発見【富山大学】
- 11月11日
- 「メタボ健診」で国保加入現役世代の生活習慣病罹患率が約10%減少
- 10月29日
- 「食行動のクセ」がGLP-1受容体作動薬の2型糖尿病治療効果と関連 岐阜大学・京都大学ら
- 10月29日
- 働く世代の足腰の健康がカギ ロコモとメタボの意外な関係を解明【昭和医科大学】
- 09月25日
- 健康関連アプリ活用で特定保健指導の成果向上 利用率・代謝改善に有意差
- 09月25日
- 令和4年度特定健診受診者「メタボ該当者」は14.8% 高齢層で高水準続く(健保連)
- 08月25日
- 肥満と糖尿病への積極的な対策を呼びかけ 中国の成人男性の半数が肥満・過体重 体重を減らしてリスク軽減
- 野菜摂取量の平均値は、256.0g(男性262.2g、女性250.6g)。野菜摂取量は有意に減少 令和5年(2023)「国民健康・栄養調査」結果より
- 糖尿病が強く疑われる人は、男性16.8%、女性8.9% 令和5年(2023) 「国民健康・栄養調査」の結果より
- 肥満の人は、男性31.5%、女性21.1%。やせの人は、男性4.4%、女性12.0%(20歳代女性20.2%) 令和5年(2023)「国民健康・栄養調査」の結果より
- 特定健診(40~74歳)受診者約3,017万人のうち、メタボリックシンドローム該当者は16.6%(男性13.3%、女性3.2%)、予備群該当者は、12.3%(男性 9.7%、女性2.6%) 令和4年(2022)「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」の結果より
- メタボリックシンドロームが強く疑われる人は、男性28.2%、女性10.3% 予備群の人は、男性 23.8%、女性7.2%-令和1年(2019)「国民健康・栄養調査」の結果より