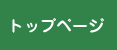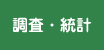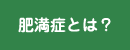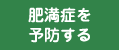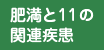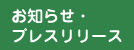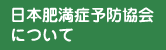世界腎臓デー 40代の4割以上が慢性腎臓病を知らない 腎臓を守るために何が必要?
2023年03月27日
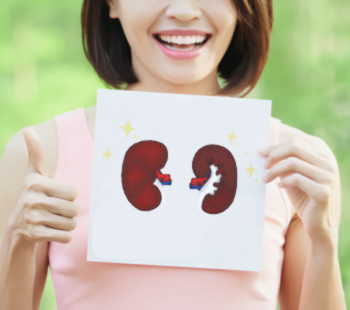
さる3月9日は「世界腎臓デー」だった。慢性腎臓病(CKD)は、糖尿病や高血圧、脂質異常症、肥満症などと関連が深く、20代・30代といった若年期からの生活習慣も発症に大きく影響している。
日本腎臓病協会などは、「腎臓病は、早期発見し、早期に治療をはじめることで、進行を防ぐことができます。まずは検査を受け、ご自身の腎機能が正常なのかどうかを知ることが第一歩です」と呼びかけている。
40代の4割以上が「慢性腎臓病」を知らない

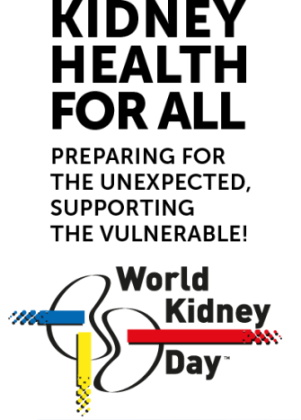
CKDは治療可能な病気です
~健診後のCKD指導動画~
日本腎臓病協会が公開している動画
~健診後のCKD指導動画~
日本腎臓病協会が公開している動画
腎機能の検査「eGFR」を知っているのはわずか17%
調査では、慢性腎臓病(CKD)を「症状も含めてよく知っている」あるいは「病名だけは知っている」と回答したのは、全体の64%という結果になった。 年齢層が上がるにつれて認知度が向上し、70代では8割以上と高かったが、若年層(20代・30代)では半数以上が知らないことが示された。40代でも4割以上、50代でも3割以上が認知していない。 CKDにあてはまる症状については、「むくみ」と回答した割合が64%ともっとも多く、次いで「タンパク尿」が58%だった。両項目ともに、やはり20~30代の若年層では認知度は低かった。 また、健康診断での腎機能と尿検査の項目については、「尿タンパク」が55%ともっとも高く、次いで「血清クレアチニン」が29%となったが、「eGFR」の認知度は17%と低かった。 調査は、全国の20歳~70歳代の一般市民1,630人を対象に、2022年11月に実施された最新のもの。 日本腎臓病協会と協和キリンは、2019年5月に締結した「腎臓病の疾患啓発活動に関する連携協定」にもとづき、腎臓病に対する啓発活動の一環として、慢性腎臓病(CKD)の疾患認知に関するアンケート調査を継続的に実施している。失われた腎臓の機能はもとには戻せない
eGFRは「推算糸球体ろ過量」のことで、腎臓のろ過の働きを示す数値。血液検査を受ければ簡単に推算できる。GFR値が低いほど、腎臓の働きが低下していることを示している。 「GFR値90以上」であれば腎臓の働きは正常だが、「GFR値60未満」になると慢性腎臓病(CKD)の疑いがあり、治療の開始を考える必要がある。 「GFR値30~59」であると、腎機能が中程度低下していることになる。腎不全への進行を防ぎ、心血管疾患を抑制するために、適切な治療を受ける必要がある。 さらに、「GFR値15未満」であると、腎臓の働きがかなり低下しており、透析療法を検討する必要が出てくる。 失われた腎臓の機能はもとには戻せないことが多い。そのため、できるだけ早期に「進行をくいとめ、遅らせる」「症状を改善する」ための治療を開始する必要がある。「GFR値が59以下」の人はお医者さんに相談を
日本腎臓病協会などは、「GFR値59以下の方は、お医者さんにご相談を」というメッセージを広め、「早期発見し、早期に治療をはじめることで、進行を防ぐことが期待されます。まずはご自身の腎機能が正常なのかどうかを知ることが第一歩です」と呼びかけている。 なお、GFR値(糸球体濾過量)を直接測定することは身体への負担が大きいため、健康診断などでは、体内で作られた老廃物であるクレアチニンの値と、年齢・性別にもとづいて推算される推算GFR(eGFR)の値が用いられている。 今回の調査結果について、日本腎臓病協会の理事長で、川崎医科大学副学長 腎臓・高血圧内科学の主任教授である柏原直樹先生は次のように述べている。 慢性腎臓病(CKD)は、糖尿病や高血圧、脂質異常症、肥満症と関連が深く、20代・30代といった若年期からの生活習慣が発症に大きく影響しています。若年層への啓発活動や、健康診断での尿タンパクの意義や、eGFRの認知を高めていくことが重要です。その一方で、慢性腎臓病に罹患している方の重症化を防ぐためのサポート体制や、早期の診断・治療の体制を全国でさらに整備していくことも望まれます。 慢性腎臓病について 糖尿病性腎症重症化予防プログラムの効果検証事業 (厚生労働省)[ TERAHATA / 日本医療・健康情報研究所 ]
掲載記事・図表の無断転用を禁じます。 ©2006-2025 soshinsha. 日本医療・健康情報研究所
- 12月18日
- NEW20~30代低体重女性で腸内細菌叢の多様性が低下 食事内容が同じでも違いが生じることを解明
- 12月18日
- NEW寿司のネタとシャリは分けて食べるべき?~血糖値への影響を調べた研究結果~
- 11月11日
- 非肥満者では糖尿病発症前に体重が減少する傾向を発見【富山大学】
- 11月11日
- 「メタボ健診」で国保加入現役世代の生活習慣病罹患率が約10%減少
- 10月29日
- 「食行動のクセ」がGLP-1受容体作動薬の2型糖尿病治療効果と関連 岐阜大学・京都大学ら
- 10月29日
- 働く世代の足腰の健康がカギ ロコモとメタボの意外な関係を解明【昭和医科大学】
- 09月25日
- 健康関連アプリ活用で特定保健指導の成果向上 利用率・代謝改善に有意差
- 09月25日
- 令和4年度特定健診受診者「メタボ該当者」は14.8% 高齢層で高水準続く(健保連)
- 08月25日
- 肥満と糖尿病への積極的な対策を呼びかけ 中国の成人男性の半数が肥満・過体重 体重を減らしてリスク軽減
- 野菜摂取量の平均値は、256.0g(男性262.2g、女性250.6g)。野菜摂取量は有意に減少 令和5年(2023)「国民健康・栄養調査」結果より
- 糖尿病が強く疑われる人は、男性16.8%、女性8.9% 令和5年(2023) 「国民健康・栄養調査」の結果より
- 肥満の人は、男性31.5%、女性21.1%。やせの人は、男性4.4%、女性12.0%(20歳代女性20.2%) 令和5年(2023)「国民健康・栄養調査」の結果より
- 特定健診(40~74歳)受診者約3,017万人のうち、メタボリックシンドローム該当者は16.6%(男性13.3%、女性3.2%)、予備群該当者は、12.3%(男性 9.7%、女性2.6%) 令和4年(2022)「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」の結果より
- メタボリックシンドロームが強く疑われる人は、男性28.2%、女性10.3% 予備群の人は、男性 23.8%、女性7.2%-令和1年(2019)「国民健康・栄養調査」の結果より